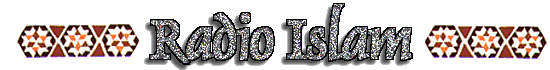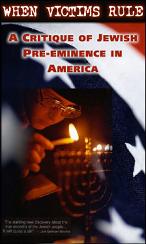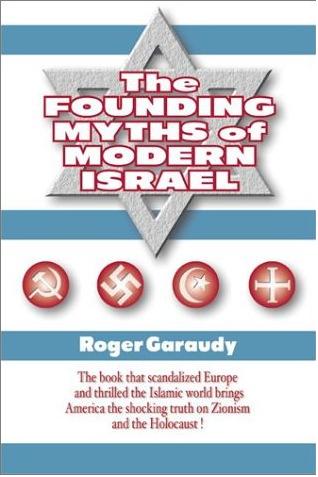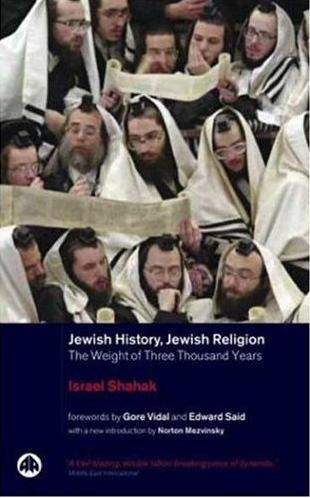『我が闘争(抄訳)』の全文
ウィルヘルム・テル
秘密結社が得てして陥りやすい特殊な危険は、その団員が自己の任務を過少に評価しやすいという点である。つまりは暗殺を行うことによって、一民族の運命が好転すると云うような意見が生れ勝なことである。斯うした信念は、或る国民が強力な圧制者の暴政に苦るしんでいる時には、或は歴史的に正当と見られるかも知れない。
そうした暴威を振う圧制者がのさばる時代には、自分を犠牲に供して国民をその圧制から救おうと覚悟した人間が生れ、その国民から憎悪の的となっている男をやっつけると云うようなことが起り得る。ドイツの偉大なる詩人が、有名な「ウィルヘルム・テル」の中で、このことを称賛しているのに引換へ、このテルの行為を目して憎むべきものであるとするのは、自分が罪を犯し、暗殺に値すべき人間たることを意識している悪漢達の共和主義的心情のみであろう。
しかし、一九一九年から一九二〇年にかけてドイツは、斯くすることによって、国民をその苦悶から救うことが出来ると考えた或る秘密組織があり、その団員がドイツ帝国の破壊者として復讐を企てる危険が多分にあったのである。だが之は根本に於て考えを誤っていた。と云うのはマルクス主義者は悪いには違いないが、単に彼等が彼等だけでドイツを革命に導いたのではなく、之を防圧すべき筈のブルジョア階級が、何等の抵抗力もない臆病者の集まりだったためであることを考えなければならない。ブルジョアが確かりしていたなれば、マルクス主義者へそのまま権力が移って行くようなことは有り得なかったのだ。思いをここに致せば右の秘密組織の持った考えは愚かしいものであったことが分るわけである。
ドイツのブルジョア階級は、この点に於て最も痛烈に攻撃を受けねばならない。彼等は少しも偉大でない指導者によって指導された革命に対して、殆んど何等なすところなく服従してしまったのだ。
或る時代の一国民が、例えばフランスの偉大なる革命家たるダントンや、ロベスピールやマラーなどに、その時代のフランス国民が屈服したと云うことは了解出来る。しかし一国民が、愚物のシャイデマンや、でぶのエルツベルゲルや、フリードリヒ・エベルトなどの愚昧な政治家の前に平服していることは、何としてもその国家並びに国民の一大屈辱と云わなければならぬ。今之等の中から一人や二人を片づけて了うことは容易だろう。しかしそうしてみたところで、殆んどそれは無意味である。なぜなれば、折さえあれば之等の人間と取って換ろうと虎視眈々たる吸血鬼が、無数に充満しているからである。