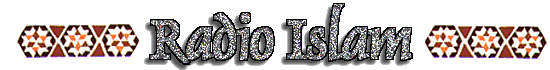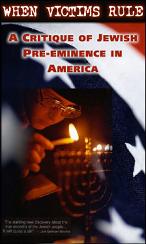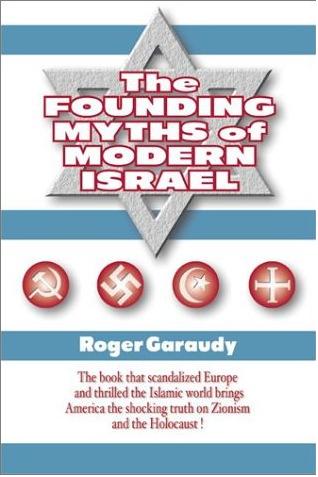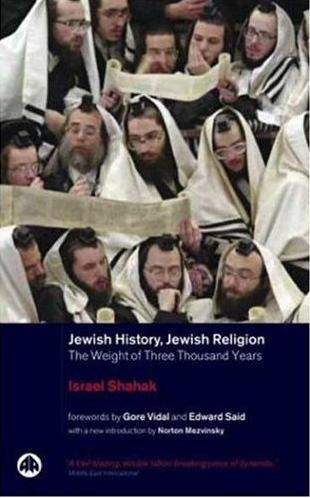『我が闘争(抄訳)』の全文
国民と祖国のみ
「国民と祖国あるのみ!」
私自身及びナチ党員のすべてにとっては、これがただ一つの信条でなければならぬし、又信条なのである。
我々は我々の民族と国家のために、子供達のために、ドイツ人の血の純潔を護るために闘わねばならぬ。我々が創造の女神から与えられているドイツ人としての使命に、立派な花を開かせ、見事な実を結ばせるために、そして祖国の自由と独立とを永遠なるものたらしめるために、飽くまで戦わなければならないのである。
私はこのことを講習会の聴講から感得したのである。フェダーの「利益の独占を破るもの」と云う講義は、大戦争は国際資本に対抗しながら戦わねばならなかったことを教えた。そしてそのことから私は、如上のスローガンを体得したのである。
別な意味で、この講習会は今一つの収穫を私に与えてくれた。それは私が平素の持論から、或る機会を捉えて、一人のユダヤ人と皆の前で討論を試みたいと申出たことから始まる。私はこの討論会に於て思い切り相手を論駁した。聴衆の大部分は私の説に賛成の意を表し、私はこの討論に勝つことが出来た。その結果は間もなくある連隊の教官として入隊を命ぜられるに至ったが、収穫と云うのはそのことではない。多数の聴衆を前にして、冷静を保ちながら演説が出来ることを実證された喜びがそれなのである。私の声はよく通った。狭い兵営の講堂では、聴衆は私の演説が聞きにくいために理解出来ぬと云う者が一人もいなかった。ここに私は一つの武器として、私の演説の才能が證明されたと云う事実を、心から喜ばずには居れなかったのだ。
私の途は拓きかけた。命ぜられた連隊へ赴任してからの私の仕事は、非常に仕甲斐のあるものだった。何故なれば、軍隊こそは私の心の中に組立てられた組織に最も近いものであったし、そこには数千の熱心な聴衆が常に存在したからである。私はそこで何回となく演説をした。そしてドイツ人の兵士の心に祖国を蘇らせ、幾百幾千の人間をその祖国と国民に復帰せしめることに成功したからである。私はこの軍隊を国民化し、訓練を強化することに全力を注いだ。この動機が後に新運動の中心人物となり得た幾多の同志を、私に与えて呉れることになったのである。
七番目の党員證
或る日私は本部から「ドイツ労働党」と云う政治結社の背後関係を調査するように命ぜられた。その晩そこでゴットフリード・フェダーが演説をすることになって居り、差当りその晩は彼の演説を筆記して来ることであった。そこで私はミュンヘンの裏街にある家の一室へ出かけて行った。この部屋こそはその後の我々にとって歴史的な重大意義を持つところとなったものであるが、この夜は二十人ばかりの、大方は下層階級に属する人達が集まっていた。斯うした結社というには余りに小さ過ぎる結社は、当時の社会不安に対抗する意味で随所に生れてはいたが、その何れもが組織的な頭を缺いたブルジョア階級固有のやり方なので、成功を収めたり成長したりする可能性は殆んどなかった。私は何の感銘も受けずフェダーの講演を聞き終った。そして帰ろうとすると自由討論が始まったので暫くそれを聞いていた。一人がフェダーに食ってかかって、バヴアリアはプロシヤから分離すべきのみでなく、オーストリアに合併すべきであると主張し出した。これは私として聞捨てならぬことだったので、フェダーに代って私がこの男に一矢を酬いると、意久地なくもコソコソと帰って行った。残った人々は私の演説を聞いて驚いたような顔をしていた。このことが終って帰ろうとすると、一人の男が駆け寄って来て「是非これを読んで頂きたい」と云って一冊のパンフレットを手渡した。
当時私は歩兵第二連隊の兵舎内で起居していた。と云っても、大抵は小銃第四十一連隊や集会や講演等に出かけてばかりいるので、そこはただ寝に帰るだけの部屋に過ぎなかった。その部屋で翌朝私は手渡されたパンフレットを読んでみた。それは「政治の目覚め」と題するものであって、一労働者が、マルクス主義の迷路と労働組合の綱領の中で、足掻きながら成長して来た過程を書いたものであった。そしてその経路は、私のウィーン時代に於ける経験を想い起させるだけのものは持っていた。
ところがそれから一週間ばかり経った日、一通の葉書が舞い込んだ。見ると麗々しく「貴下をドイツ労働党の一員として入会を認める」と書いてあって、尚これに就て何等かの意見があれば聞かせてほしいと断り書がしてあった。私は思わず苦笑した。何故なら私はどんな党から勧誘を受けても、それに加盟する気はなかったからだ。私は私だけで一党を樹立しなければならぬと決意していた。
水曜日の晩に委員会があるという通知だったので、私は手紙なんか断るよりも、行って口頭で断った方がよろしいと思って出かけて行った。会場たるアルテ・ローゼンバットの料理店では、半ば壊れかけた薄暗い瓦斯ランプの下で、四人の青年がテーブルを囲んで待っていた。私が行くとその中の一人が立上って、新党員たる私に親愛の情をこめた挨拶をした。この男が例のパンフレットの著者だったのである。「全国委員長」の名はハーラーと云い、私が行ってから間もなくそこへ姿を現われた。ミュンヘン区の委員長はアントン・ドレクスラーと云う青年であった。
顔が揃うと会議が始まった。先ずこの前の集会の議事録を読み上げてそれを承認し、続いて会計報告があった。それに依ると党の全財産は何と七マルク五十ペニッヒ(約三円五十銭)しかなかった。それから各地から来た手紙(と云っても三本であるが)を朗々と読み上げ、各人が暫らくその手紙に対して討論した上、何れも回答を出すことに決定した。
私はその事々しい様子を見ながら、初めは吹き出したくなった。どんな角度から見ても、ドイツ労働党などという堂々たるものではない。そこらにザラにある貧弱なクラブの一種に過ぎない。このクラブへ私を入会させようと云うのか。
それらが済むと今度は新党員たる私への討議が始まった。そこで私は色々質問して見たが、党として持っているものは原則だけで、そのほかにはまだ何の計画も、党員名簿も、リーフレットも、いやゴム印すらも持っていないことが分った。
しかし私は最早笑うことが出来なかった。この貧弱極まる党の姿は、そのまま現在のドイツ人の悩みを象徴しているように思えて来たからである。組織や数は如何様ともあれ、この人々の結合は祖国ドイツのために尽そうとする大きな熱意から出発しているものには間違いなかった。そこで私はタイプライターで打たれた党の主張を大急ぎで読み通した。そこには智識を所有してそれを駆使しようとする大乗的な欲求は見当らなかったけれども、何等の智識を欲求する熱が躍動していた。切実に何ものかを求める内心的な力が強く感じられた。
考えてみれば私も、煎じつめればこの人達と同様な考えの下に、既成政党とは違った、全然新しい生命を盛った新党の誕生をのみ思い続けて来ていたのである。
皆と別れて兵営へ帰ってからも、帰って後の二三日中も、私は常にこのドイツ労働党に加盟すべきか否かに就て思い煩った。これは非常に決心のつきにくい問題であった。屡々述べた通り私は、如何なる党にも加盟しないと云う断乎たる決意を持っていた。従って私の理性は頑強にこの党に入会することを拒絶した。しかしその反対に私の感情は、不思議とこの党へ引きつけられるのである。
私は一度斯うと決心した以上は、その後に於て絶対に変更をしない人間である。従って私の決心は常に確乎たるものでなければからなかった。即ち私はこの党に加入するか否かを私の永久の問題として決しなければならなかった。それだけに私の考慮は他人の想像以上に真剣だったのである。
兎角する中、ドイツ労働党のような、こんな小さな党なれば、自分の思いのままに料理出来るということを考え始めた。舊来の政党からは何物をも期待出来ぬ。しかしこんな小さなものからでも、国民を更生させる新運動を起し得ぬと誰が断言出来る。必要なのは、新しい世界観と、人を動かし得るスローガンである。
ここまで考えは進んだけれども尚未だ決心がつきかねた。
この党に入り、この党を自分の思うままに作り上げることが出来るとしても、それ以上の何かが私に出来るであろうということを考えたからである。何よりも先ず私が無名の一軍人であり、私一個の生死は私の周囲に何の痛痒をも感ぜしめはしない。つまりは生きようが死のうが、だれも問題にしないところの平凡な人間である。のみならず私にはこれぞと云う学歴がない。知識階級の人間共は、小学校をもロクに卒っていない私などの云うことを、頭ごなしに軽蔑してかかっている。このことも私を躊躇させる一つの原因となっていた。
斯うしてその後二日間私は苦しい程に迄考えつづけた。しかしその結果確乎たる決心を握ることが出来たのである。これは私の生涯を決定するであろう一大決心であった。しかし一旦決まった限り最早再考の余地はない。
私は決然としてドイツ労働党に入党することを申出た。そして私の手には、記念すべき「第七人目の仮党員證」が手渡されたのであった。