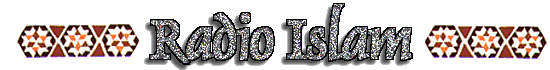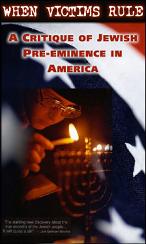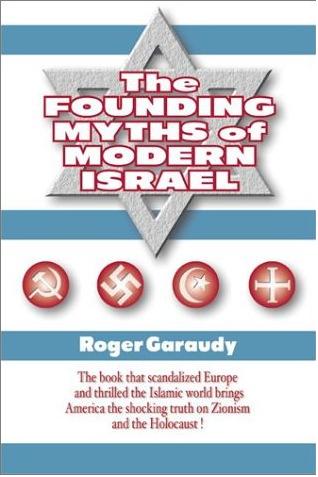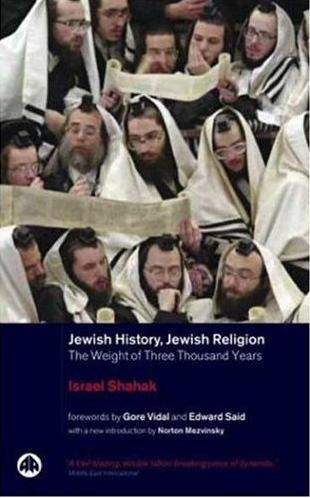『我が闘争(抄訳)』の全文
三転して画家志願
この頃から、私の弁舌上の才能は、そろそろ芽を吹き始めた。議論好きな私は、友達と火の出るような議論をすることによって、益々私の弁舌を磨くことになったのである。そして、いつとはなしに私は、一つの弁論会でもあると、その司会者の位置に据えられるようになった。
この弁舌の才能の萌芽と共に、もう一つ別な芽が萌出したのもこの頃である。それは絵画に対するものであった。図画は自分でも好きであり、父も亦私のこの才能は強く意識してはいたが、折角乍らオーストリアの学校では、図画などは付け足りのような科目に見られていたし、父自身もまた私の才能には目をつむって、私を父が経て来たと同様な文官生活に立たせようと思っていた。けれども私は父のこの希望には容易に従う気にはなれなかった。何故なれば、若い官吏や下役というものは、常に上役に使われるものであって、自分自身の生活の主人公になることは出来なかったからである。
一方学校での科目は、私にとっては馬鹿馬鹿しい程容易なものであったために、時間が有り余って困った。そのため私は、屡々森や野原へ出て、学校をおっぽり出しておいて悪太郎共と遊び回った。現在の私の敵共が私の生涯を詮索して、この少年時代の私を発見したなれば、ヒットラーは小学教育もロクに受けなかった無学な男だなどと、卑しい詭計を無数に探り出すことが出来るであろう。だが私にとっては、この時代の追憶程楽しく恵まれたものはない。
十二歳になった時、私は画家として立とうという決心が、心の奥で固く築き上げられていることを知った。何も知らない父は、再び文官になるようにすすめたのであったが、その時に初めてキッパリと之を拒み、更に画家として立つ積りだということを断言した。この私の意外な希望を聞いて、父は顔色を変えて驚いた。
「なに画家になる? 芸術家になるんだって?」
と云った切り、暫くは呆れて物も云えぬように黙っていたが、次の瞬間には如何にも性格の強い父らしく、激しく之に反対した。
「いかん、画家なんか断じていかん。俺が生きている限り絶対にいけない」
この強い父の反対は逆に私の決心をより一層固めることになった。老境に入った父のその時の表情は実に苦しそうであったが、父を愛している私にとっても亦、このどうにも修正の利かぬ決心は苦しいものであった。父は言葉を尽して私の決心を捨て去らせようとした。父は父としての権力を以てしても、この希望を思い止まらせようとしたが、私はこの権力に対して小さな威嚇行動を以て応じた。つまり私の望みを叶えて呉れないのなれば、もう学校の勉強なんかしないという宣言である。この時採ったこの行動が、果して正しいものであるかどうかは分らないが、私はすっかり学業に見切りをつけて、ただ好きな地理と歴史だけに力を入れた。中にも歴史は最も気に入りであっただけに、優秀な成績をあげたものである。