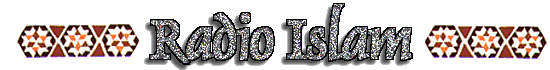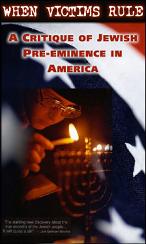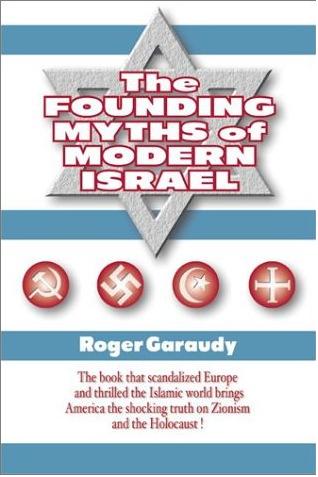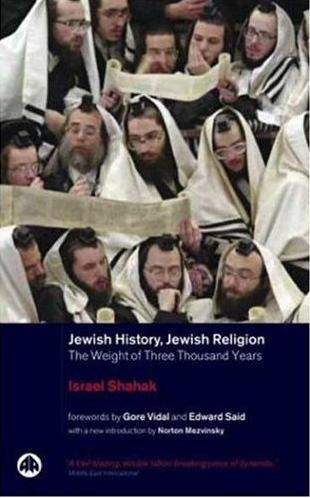『我が闘争(抄訳)』の全文
再び傷つく
一九一八年の八月、私は三度びこの地点に立った。断じて攻勢を捨てぬ我軍は容易に敵の蹂躙を許さなかった。しかしこの頃になると、兵士の間では既に盛んに政治論か交されるようになって来ていた。国内からの毒素は遂に完全に第一線にまで及んで来たのだ。
十月十三日の夜から十四日にかけて、イギリス軍はイーブルスの戦線で毒ガスを発射して来た。それは我々が始めて経験するところの「黄十字」と呼ばれた猛烈な糜爛性毒ガス弾であった。私はその毒ガス弾の効果を調査する様命ぜられた。そこで私はヴェルヴィック南方の小丘に趣いたのであったが、その夜は夜つびてこの毒ガス弾に見舞われ、真夜中頃までに、既に我々の半数は仆れた。そしてその中の何人かは遂に永久に眼を開かなかった。
夜明けに近付く頃、私も亦猛烈な苦痛に見舞われ始めた。如何にしても我慢がならないので、朝の七時頃よろめきながら後方へ退かざるを得なくなった。まるで眼全体が燃える石炭のように熱くなりあたりは真暗になってしまった。私は間もなくベルリン北方の海岸地方にあるボメラニアのバゼヴァルクにある病院へ移された。そこで私は、ドイツ人としての生涯を通じての一大不名誉に遭遇しなければならなかったのである。
私は失明するのではないかと思った。しかし幸いにも視力は幾分回復され、痛みも次第に薄らいで行った。再び絵が描けるようになる迄、是非とも回復させなければならぬと思って、私は真剣に養生をし、全快を神に祈った。
その頃の国内の空気は異常な不安を孕んでいた。今に何か持ち上るに違いないと云う予感が頻りと私の胸を往来した。果然この年の十一月になって、大変動が我々を見舞ったのである。この海岸町の病院の前を、数台のトラックに分乗した船員たちが、数人のユダヤ人に指揮されながら、手に手に赤旗を振り声一杯に革命歌を高唱しつつ通っていたのである、ああ遂に来た!と思った。しかし私は、どうかしてこの革命的暴動が、この地方だけの一小事件であって呉れることを、ひたすらに祈った。が、それは無駄であった。噂は次第に高まり、浪のうねりは日増しに大きくなり、遂に最も怖れていた革命の大津浪は、ドイツ全土を襲うに到ったのであった。
引続いて前線からのニュースが入って来た。事茲に至っては、最早降伏を考慮するより外あるまいと云うのである。おお降伏!今日まで絶対優勢裡に戦って来た我々が、突如として白旗を掲げねばならないとは―果してそんなことが可能であろうか。
十一月十日、一牧師が悲痛な顔をしながら、我々の病院を訪ねて来た。そして我々はその牧師から既に、起きてしまった一切の事態を知ったのである。私はひどく昂奮しながらその牧師の話を聞きに行った。牧師は木の葉のように打震えながら、ホーヘンツオルレン王家が退位したこと、祖国は最早帝国ではなく、あの盗人共の共和国となったこと等を話すのを聞いた。最後に牧師は、如何に王家がドイツのために全力を傾けて尽したかを物語って、しばし涙にくれていた。そして、もう我々は戦争を継続出来ないこと、戦敗国となった以上は、勝利者の慈悲に縋らねばならぬこと、祖国は当分連合国の圧迫を甘受せなければならぬこと等の説教を始めた時、私はよろめきつつ立上り、寝台へ戻って火の様に熱した頭を夜具の中に埋めたのであった。