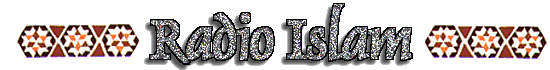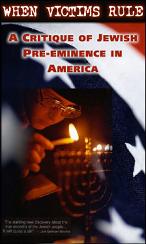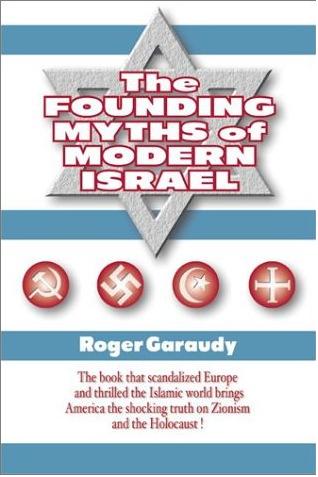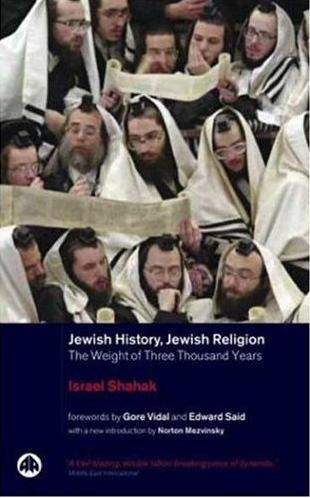『我が闘争(抄訳)』の全文
「ドイツよ すべての上に!」
久しい間私の体内に鬱屈していた希望が満たされる日が来た。少年時代から青年時代に亘って、燃え切っていた私の愛国熱が、そのはけ口を与えられる日は来たのである。最早私は、私の仕事にしがみついて、拱手傍観している時ではなかった。私は幾度か国家「ドイツよ、すべての上に!」を歌い腹の底から「ハイル」を叫んだ。私は遂に立上った。
素より私は、久しく憎み続けて来たハプスブルク王家のために戦うものではない。私は私の祖国であるドイツ帝国のために、ドイツ国民のために、喜んで線上の露と消える決心をした。
1915年8月3日、私は決然としてルドウィッヒ三世陛下に、バヴァリア聯隊へ編入して頂きたいという歎願書を奉呈した。私はその結果を一日千秋の思いで待ち受けた。そして早くもその翌日、回答は渡されたのである。私は許可されたのだ。許可証を握りしめて、私は文字通り狂喜した。許可証を握る手の震えるのをどうしても止めることが出来なかった。数日後、私は軍服を着ていた。遂に一個のドイツ帝国軍人となったのだ。そしてこの軍服は、それから六ヶ年の間私に身につけられていた。斯くて私の生涯の中で、最も大きな、重大な時期が、到頭その緞帳を繰り上げ始めたのである。
私にとって気がかりなことは、ただ一つしかなかった。それはぐずぐずしていて、第一線に立つ日が遅れはしないかという心配だけだった。それだけがただ私の心の静けさを掻き乱すだけで、魂の凡ては最早第一線に飛んで行っていた。
間もなく我々はミュヘンを後に行進を始めた。愈々ドイツ帝国をその強敵から守るために、西部戦線への進軍は開始されたのだ。そして進軍中に、私は生まれて初めてライン川を見た。ドイツの歴史と共に永久に流れるところのライン川は、流石に私の心を打たずにはいられなかった。
寒い雨がじめじめと降る夜、我々の一隊は黙々として沸泊国境のフランダースを進軍していた。間もなく夜明けが来ようとしていた。その時突然我々の頭上をシュルシュルと激しく空気を裂く音を立てて一発の砲弾が掠めて飛んだ。と同時に小銃や機銃が雨のように降り注いで来た。之が初めて味わう戦場の音であり、味であった。我々は時を移さず野をよぎり、敵の防塞を遮二無二突破して敵陣に突っ込んだ。そして文字通り強烈な白兵戦が展開された。我々は最初の戦いに、先ず敵に勝ったのである。
引続き必死の戦いが続けられた。その激しい銃砲声の絶間に、どこからともなく歌声が聞こえて来た。その声に和して、いつとなく皆が力いっぱい歌っていたものは、
「ドイツよ、すべての上に!ドイツよ、世界のすべての上に!」の国家であった。
四日間激しい戦争が繰り返された。そして我々は交替のために後方陣地へ退いた。が、その時の皆の歩調は、四日前とは全く違ったものになっていた。銃砲の洗礼を受け、死の恐怖を潜り抜けて来た偉大なる経験は、わずか17歳の少年たちの歩調すらも、全く大人と同じに確りしたものに変えてしまっていたのである。
これが序曲であった。
しかしこの喜びもロマンスも感激も、やがて日毎繰り返される凄惨な戦闘に依って、一切死の恐怖に被はれてしまった。私も亦死の恐怖を感じないではなかった。けれどもその本能的な自己保存の声が心の中に起これば起こる程、それに対する私の反抗心も強まった。私の義務感は1916年の冬までには、完全に恐怖心を征服して、全く「意思」が支配者となることが出来た。
これは単に私だけに起きた心の変化ではなかった。ドイツの全軍に亘って、この変化は起こった。要するに一戦毎にドイツの全軍は鉄石の意思を持つ軍隊として鍛えられて行ったのだ。この英雄的な精神こそは万古を通じて燦たる光芒を放つものとも云えるであろう。
私は既に軍人である。だからなるべく政治を論じたくはなかった。しかし銃後から送られて来る新聞は、常に私の心に政治を考えさせねば措かぬものを持っていた。
戦争の日数が経つに従って、新聞にはこんな記事が時々現れるようになった。「戦争は、苟も文明国人と称する者のやるべきことではなかった。ドイツの軍人は実に勇敢である。しかしこれは既に定評のあるところであって、何も今更我々文化人が驚くにも当たらないことである。とまれこの戦争は我々には何等の関わりを持つものではない。」
この新聞記事は私に異様な感じを与えた。すると間もなく銃後に於ける民衆が、戦争熱を高める為の示威運動やその他あらゆる催しに対して次第に反対の気勢をあげ始めたことを報じて来た。この事実は饒舌な新聞に益々油を注ぎ、両々相俟って一層この反対気勢が広がるかに見えた。実に許し難い罪であり、絞罪にも値すべき非国民的態度であるにもかかわらず、不可思議にも之等の民衆も新聞紙も何等の処罰を受けぬのみか、彼等のこの反戦運動は益々盛んになる一方であった。遂には我々が命を賭して勝ち得た大勝利の戦勝祝賀を拒む者すら出来て来たのである。
私には之は解き難い奇妙な現象と見られた。戦争熱は陶酔である。もしこの夢が一度破られるようなことになったら、最早それは容易な力では元へ取り戻すことは不可能である。而してその結果はどうなるか。これは最早云うまでもないことである。
私自身としては、戦争の喜びを高揚したり、前線の将兵を勢いづけるような何等の手段も報じられていないということが、ひどく腹立たしかった。そして、こうしたことが、組織的な何者かの指揮に依ってなされているのが、どうしても理解出来ないので苦しんだ。