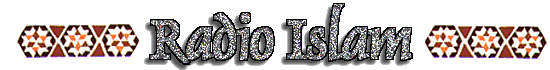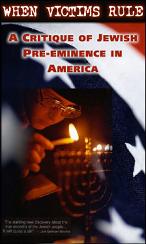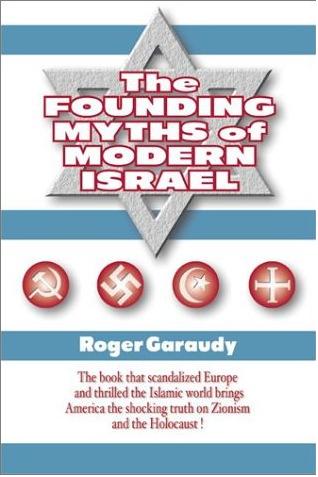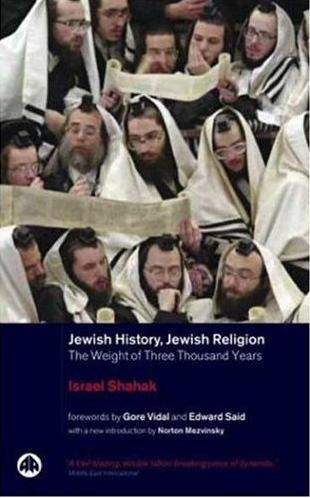『我が闘争(抄訳)』の全文
日露戦争への感激
この戦争は残念乍ら南阿軍の敗北に終って幕を閉じた。私の闘争に目覚めた血はまだ強い力で体内を駆けめぐっていた。その中に日露戦争が起ったのである。
日露戦争が起った時は、私はもうずっと凡てに成長していた。素々ハプスブルグ家を憎み、その親スラブ主義を憎悪していた私にとっては、ロシアそのものに少しの好意さえも持っていなかった。というよりも矢張り憎んでいた。殊にその強力を恃んで、東洋のまだ充分発育していない日本を攻撃することには、一種の公憤を禁じ得なかった。それだけに、世界一の強国と歌われていたロシアに、憶することなく敢然として矛を採った日本に対しては、絶対的な支持を與える気持になれた。戦いは世界の予想を裏切って、日本の意外な大勝に帰した。私はこの報を得て雀踊りした。何故なれば、ロシア帝国の敗北は、取も正さずオーストリア・スラブの弱体化であり、ひいてはそれが破滅の運命を意味したからである。
さて——世界大戦前のドイツ人が、その指導者の指示に従って、商業的世界征服を信じたことは、商業的にドイツを発展させたことは確かであるが、その一面に於ては、政治の法則にかなったすべての見識や、意志や、決断力を忘れさせる結果を招いた。要するにドイツ人は商人となったことに依って、ドイツ人たる強さを失ったのである。この弱体化が遂に彼の世界大戦を招き寄せる大きな原因となってしまったのである。
しかし私は今一歩進んで、このことを考える。嘗て、そして常に英雄的であったドイツが、何故斯くも弱い国家になったか。それは根底に於いて、マルクス主義の毒薬を注射されたからである。
私がウイーン時代に親しく目撃し、親しく体験したところのマルクス主義の大きな破壊力は、遺憾乍らドイツ国家にも既に浸潤して来ていたのだ。国際的平和主義の仮面を被ったこの悪魔は、巧みに偽装してドイツ政府の中に忍び入り、まんまと我々の指導者達を麻酔させることに成功していた。
このことを何も知らないドイツ国民は、「我々の上には何も起こる筈がない」と安心し切っていたが、これこそ噴火山上で昼寝をしているようなものであつた。私はこの臆病者達の預言を破壊して、足元に差し迫っている危険を忠告することに之務めた。そしてそのことは今日に於いても尚続けられている。只現在のそれは、その当時と比べて大規模な忠告と、マルクス主義への徹底的な闘争が行われているだけの相違である。
1913年から14年にかけて、私は確信を以て次のことを警告した。即ちドイツ帝国の安危は、マルクス主義と四つに組んで、食うか食われるかの一大決戦をすることに掛かっていると。この主義は殆んど目に見えない。然し性の悪い白蟻のように、何時の間にか国家の屋台骨を食い荒らして、それを崩壊へ導く恐ろしい力を持っているものなのだ。
かかる憂慮に心を痛めている時に、バルカン戦争(注―バルカン半島に起った二回の戦争、第一回は伊土戦争に敗れたトルコの弱体化に乗じ、1912年ブルガリア、セルビア、ギリシア、モンテネグロの三ヶ国が同盟を結び、突然トルコに宣戦して勝利を占め、ロンドン条約の結果トルコからバルカン半島の大部分を割譲せしめた。第二次はこの割譲分割に当たって、ブルガリアが余りに過大な要求をしたため、他の三国はルーマニアと結んでブルガリアを攻撃し、トルコも亦失地回復を企図してブルガリアを攻め、遂にブルガリアが屈してブカレスト条約を結ぶに至ったもの)が起った。この戦争は間もなく一応の結末を見たが、その結末からは、更に次の一層大きな事件が持上るであろうという懸念が充分に見て取れたのであった。今に何か大変動が起る、今に―という気持は、毎日まるで悪夢のように私の心を襲った。この不安は一時私を熱病患者のようにした。
しかしこの不安と悲しみは、そう長くは続かなかった。苦しみ抜いた私の心は、やがてその不安が一つの希望に代わりつつあることを知った。諦めから翅望への変化であった。そして私は、所詮避け得ることの出来ぬ不幸であるならば、徒に日を経るよりも、一日も早く我々の頭上にそれが見舞って来る方が良いと思うようになった。