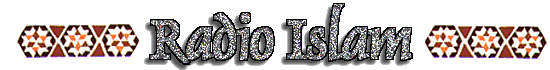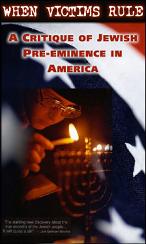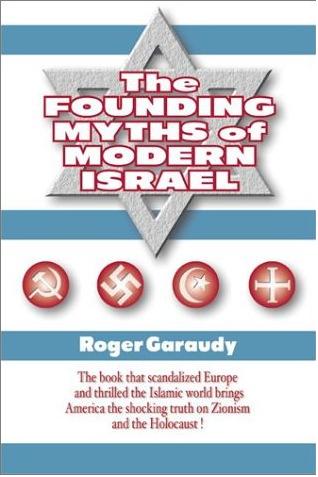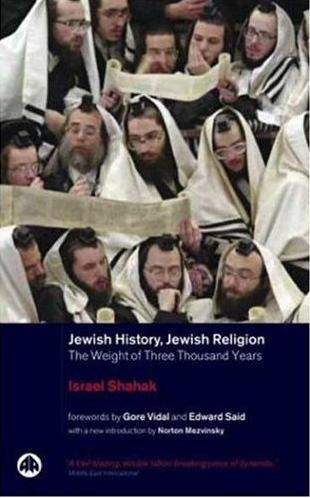『我が闘争(抄訳)』の全文
ユダヤ人の黒幕
斯うして次第にマルクス主義者の全貌が、明かな形を浮び上らせるに従って、私は今一つ重大なものを発見したのであった。云わば之こそマルクス主義の元凶であり、怖るべき赤色参謀本部たるべきものだったのである。ユダヤ人への新しい認識がそれだ。この民族こそは社会主義民主主義の背後に潜みつつ、之を自由に操縦するところの黒幕そのものだったのである。私は遂にこの主義を発く唯一の鍵を手にすることが出来たのだ。
ユダヤ人、ユダヤ人が果たして何物であるかを知ろうと思ったなれば、何でも構わず偽れる物の仮面を引っ剥がせばよい。そうすれば濛々漠々たる社会的議論の中から、歯をむき出した、狡猾そのものの如きユダヤ人が醜怪な顔を現わすに違いないからだ。
私は始めてこのユダヤ人に対して、特別な考え方を抱き始めたのが何時頃からであったかを明瞭に思い出すことは出来ない。私は家庭に於ても格別ユダヤ人を攻撃するような話を聞いたこともない。小学校時分にクラスの中に一人のユダヤ人がいたが、ただ何となく超然と取り澄ましていて、皆と交際しないために、嫌な奴だな、と思った位のことである。
政治上の問題で「ユダヤ人」が取り上げられていることは、十五六歳時分に既に知ってはいたが、私は少年時代を過ごしたリンツ附近には、殆んどユダヤ人は居住していなかったし、よしんば住んでいても、そうドイツ人と容貌が変っていると云うのでもなかったから、私はユダヤ人もドイツ人だとばかり思っていた。私のこの考えは勿論不完全なものには違いなかったが、私としてはドイツ人とユダヤ人との相違は、ただ彼等の宗教が我々のそれと変っていることだけだろうと思っていたのである。従ってユダヤ人が到る処で虐げられ迫害されると云う様な話を聞くことがあっても、それは単に宗教が違うためだけで、そんな目に会わされるのだと思って、寧ろ彼等に同情していた程であった。要するに少年時代の私は、ユダヤ人に対する組織的な戦争が、同じ国土の中で激しく展開されているということなどには全然無関心のまま、その戦場の真只中であるウイーンへ出て来たのである。
ウイーンへ来てからでも、暫くは眼に見える絢爛たる都会の姿と、差当ってパンを稼ぐための労働とに、私の耳目の大方を奪われて、この巨大な都会に、どんな種類の人間が居り、どんな種類の層があるかなどはテンで知らなかった。その後暫く経ってから、やっとこの首都のみに限らず、広く反ユダヤ主義が展開されていることを知るようになったが、その時ですら私は、前述のような人道的な観念から、之等の運動に参加する気もなく、又人から勧められても拒絶し通して来たのであった。
ユダヤ人への認識
ウイーンへ来た最初私が熱心に読んだ新聞は、当時世界新聞とまで云われていた「ノイエ・フライエ・ブラッセ」や「ウイーナー・ターゲプラット」などであった。しかしこの両新聞とも殆んど盲目的にハプスブルグ王家を崇拝しているので、ハプスブルグ王家に対して私の反感が募るに従って、追追権力におべっかを使うこの新聞に厭気がさして来た。結局は私にとって無縁の新聞であると思うようになったのである。
私はウイーンにいても、ドイツ帝国の政治や文化或は歴史等に関するものを熱心に読み、且つ研究すると同時に、日を追うて興隆の途を辿るドイツを我が事のように誇りに思った。それだけにオーストリア帝国の何となき衰頽振りが心の中で皮肉に対照されるのであった。斯くもドイツを愛する私にとって、ドイツ帝国の外交は実に素晴らしいものであったが、その内政に至っては屡々憂慮すべきものを見出さざるを得なかった。
ウイーンに於けるドイツ皇帝ウィルヘルム二世への反感は相当なものであり、その評判は決して良くはなかった。私はウィルヘルム二世の中に、単にドイツ皇帝のみでなく、偉大なドイツ艦隊の創始者をも見ることが出来た。私にとっては実に尊敬すべきカイゼルであった。然るにウイーンの新聞などが、小さい地方的な宮廷の勢力に尾を振って、ドイツのカイゼルを公然と攻撃する記事などを載せたのを見ると、若き私の血は憤激に煮えたぎるのであった。
殊に有力な新聞が、特に意識的にフランスを褒めそやすことは我慢がならなかった。その記事には全くドイツ人には耐えられないような言葉や文字が使用されることが屡々であった。その結果私は、反ユダヤ主義の一新聞「フォルクスブラット」に走らざるを得なくなった。この新聞のドイツのカイゼルに対する凡ての記事は、極めて公正な態度を採っていたので、そのことが私を引きつけたのである。尤もまだ私は、この新聞の反ユダヤ主義には左袒出来なかったが、それでも小型ながら、清潔な「フォルクスブラット」の時事評論は、私に考えさせるいろんなものを提供してくれたのである。
この新聞を読んでいる中に、これがウイーンの運命を支配していた人物とその運動、即ちキリスト教社会党のカール・リューゲル博士を知らしめる仲立となったのである。始め私はこの博士がやっている反ユダヤ運動を反動的なものとしてどちらかと云えば嫌っていたのであるが、追々とその意見を聞いたり読んだりしている間に、私の意見は次第に変化を来すに至り、遂にはリューゲル博士を、あらゆる時代を通じての、最も偉大なるドイツ人の市長であると考えるようになった。
キリスト教社会主義の目的が明かとなり、この主義へ私の心が同感を向けるようになると共に、今迄抱いていた反ユダヤ主義への反感も亦修正されざるを得なくなって来た。これは私にとっては実に大きな変化であった。白いものが黒くなろうとするのだ、私はこの変化が果して正しいかどうかに就て慎重に考えた。理性と感情とは二ケ月間にも亘って、私の心中で戦ったが、結局は感情が勝利を占めることになった。この時からして私は反ユダヤ主義の翼下に立つことになったのである。
ウイーンの街を歩いていた私は、或日トルコ人の着るような長いガウンを着た、黒い捲毛の人間に出会った。私は突嗟に「これがユダヤ人であるかも知れぬ」と思った。それと同時に「これも亦ドイツ人なのであろうか」と云う疑問が湧き上った。そこで私は、いつもの私の習慣に従って、この疑問を書物に依って解決つけるべく、早速数種の、反ユダヤ主義パンフレットを買い集めて研究に着手した。しかし之等のパンフレットは、何れも強い調子でユダヤ人を攻撃してはいるが、その書かれていることには、言葉程強い理論が含まれていなかった。この理論の浅薄さと弱さとは、私を全的に承服させることが出来なかった。何とかもう少し心から納得の行くような確乎たる理論がないものであろうかと、私は数ケ月の間、解け切れない疑問のために苦しんだのである。そしてその解決されざる心は余りにも激しいユダヤ人への迫害事実を、真正面から是認することは、或は正義に反するのではないかとの疑惑をも誘い出した。とは云え、この研究は決して無意味ではなかった。私は既にユダヤ人が決してドイツ人ではなく、奇妙な宗教を崇拝するところの、全然異なった民族であることに目覚めたからである。それと時を同じうして、今迄気もつかなかったユダヤ人を、街の至るところで見受けるようになった。人口二百万のウイーン市民の中に、その約一割の二十万人に相当するユダヤ人が住んでいることをも、この頃になって知った。
私は解けぬ疑問のまま暫くユダヤ人を眺めて来たが、軈てこの逡巡にも断を下される時が来た。それは彼等ユダヤ人が、ユダヤ民族のためのユダヤ王国を作ろうとする、シオニズム運動に狂奔していることを知り、ウイーン市内に於ても、広汎な範囲に於てこの運動が展開されていることが知ったからである。
シオニストであるユダヤ人と、シオニストでない側のユダヤ人との間には、事々しい理論や実際運動の葛藤繰り広げられていたのであったが、その葛藤をよく研究してみると、それは全く虚言と虚偽との上に組立てられた、意味深長なる一つの芝居であることが分った。この民族が二手に分れて、如何に論戦してみせたところで、一皮剥けば同じ穴の貉であって、役者同志の間には立派に一つの共通な目的が貫流して居り、この争いは与論を惹き起すための欺瞞興行に過ぎなかったのだ。このことを知って始めて私はユダヤ人の心の不潔さに胸をむかつかせたのである。
之はただ一例であって、愈々ユダヤ人の本体を知ると、次から次へ、この民族が如何に指弾され、如何に嫌悪されるに足るだけの、不純不潔な様々なものを持っているかと云うことが、益々明瞭になって来た。彼等の服装が不潔で、その容貌が極めて非英雄的なという様なことだけではなく、最も鼻持ちならぬ点は、自ら「選ばれたる民族」と称するこの人種が、道徳的に最も大きな不潔性を以ているということであった。
凡そふしだらや放蕩の存在するところには、必ずユダヤ人の姿なり影なりが見受けられた。特に文化生活方面に於てこの傾向は著しいものがあった。不健康極まる文学や、みだらな芸術、全くこの世界に無用と思われるような愚劣な演劇が不思議にも多数の人々の喝采を博していたが、之等の凡ては人口の僅か百分の一にも充たないユダヤ人によって、すっかり牛耳られていたのである。この怖ろしい害毒は、コレラのような伝染力と殺人力とを持っていた。然もその病原菌は休むことなく培養され、無数に散布されていたのである。
前述した「世界新聞」も亦この一味だったのである。表面的にはこの新聞は極めて自由主義的な態度を表明していたが、仔細に検討するときは、それは巧みなカモフラージュに過ぎなかった。この新聞が強く攻撃されることがあっても、或る時は問題じゃないと云った風に黙殺したり、或は極めて尊大な態度で応酬したりするのは、彼等の思い上った意志がそうさせるのではなく、そんな態度をとることが、彼等を偉人に見せる唯一の手であることを承知して行う、実に狡猾な下劣なトリックであることが明かとなった。試みに見よ、彼等は常にユダヤ人の作家に対しては、筆を惜しまず賞賛するに引替え、彼等の悪評の目標は判古で押したように、ドイツ人作家にのみ向け垂れているではないか。彼等はフランス的な文化に対しては讃辞を惜しまないが、ドイツ的なそれには黙殺と悪評のみをしか与えないのである。要するに彼等はドイツ的なあらゆるものに対して、故意にこれを軽視して観ようとすることに努力している。そして又常に国際的であろうとすることに努めていたのである。