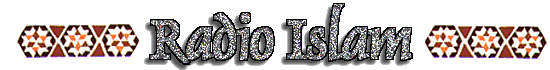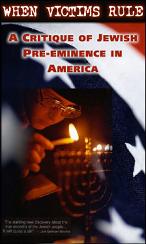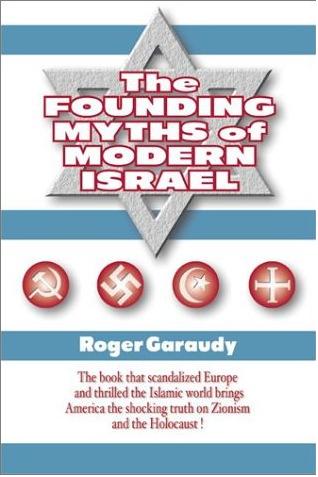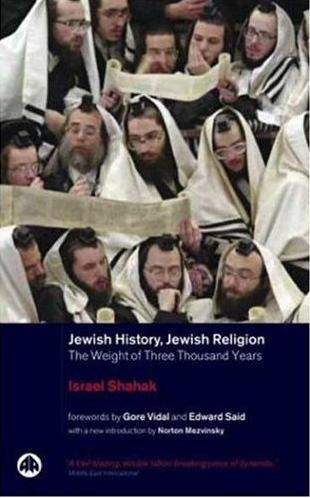『我が闘争(抄訳)』の全文
オーストリア憎悪益々募る
ドイツ人運動の指導者たちは、この大切な機微に通じていなかった。しかるに彼らの相手であるキリスト教社会主義社達の幹部連は、大衆というものの性質をよく理解していた。そのために、常にドイツ人運動者に対して優位の対抗が出来たのである。しかし、この幹部連と雖も、ユダヤ人に対する攻撃の点では大いに誤った概念を持っていた。彼らはユダヤ人を攻撃する点に於いて相当激烈ではあったが残念なことにその攻撃武器は「宗教」であった。宗教的にユダヤ人を攻撃することは決して無力ではないにしても、それはユダヤ人の外郭を衝くものであって、心臓部を狙う根本的な攻撃とは云えなかった。ユダヤ人を攻撃するには、何としても民族的な立場からするべきである。
宗教的に攻撃されることなどは、ユダヤ人にとっては蛙の面に小便であって、必要とあらば洗礼の水一滴を以て、彼等に加へられんとする抑圧の矛先を転じ、ユダヤ主義を擁護出来る程極めてお手軽なものだったのだ。つまり彼等の攻撃方法は、爪の垢ほどもユダヤ人を心配させることはできなかった。若しもキリスト教社会主義党の指導者たちが、大衆の如何なるものであるかを理解していたと同じ程度に、反ユダヤ運動を理解していたとしたら、更にまたもっと国家主義的な傾向を取り入れていたとしたら、この主義なり党なりは、ドイツ民族の運命を変えるということに成功していたに違いないと考えられるのである。
私は以上の様な見解を抱き、且つこの見解に対しては不抜の確信を持っていた。しかし私のこの確信は不幸にして、何処に於ても正しく理解されなかったし、オーストリアの政党にも採用されなかった。私はこの空しき確信を抱きながら、差当って何をなすべきかに悩んだ。若し政党が真に有力なものであるなれば、私は信じ得る政党に身を投じてこの確信を実行に移したかも知れないが、そんなものはもとよりあろう筈もなく、皆無力の凡頭を並べているだけに過ぎなかった。このことは一層私のオーストリアに対する憎悪を募らせる結果になった。結局オーストリアにいては何一つ出来はしない。ドイツ民衆の運命は、この土地以外の土地、即ちドイツ国内に於てのみ決定し得られると云うことを知った。
オーストリア国家は絶対的にドイツを拒否している。ドイツ的でないものに対しては惜しみもなく保護の手をさしのべるが、ドイツ的な一切のものは、之に強い圧迫を加えんとしていることが益々明かとなって来た。殊に首府たるウィーンには雑多な民族、例えばチェッコ人やポーランド人、ハンガリア人、ルテニア人、セルビア人、クロアチヤ人などが雑然として巣食い、それらの民族が又無軌道に混血児を生んで民族の純潔さが日一日と失われて行くばかりか、街のどこへ行ってもユダヤ人が目につくので、そんなことだけでも最早私はウィーンの街に居たたまれない嫌悪を感じ始めた。
私はウィーンにいる間中、常に幼い頃聞き覚えたバヴリア地方の、ドイツ語特有な響きを忘れることが出来なかった。どう努力しても、ウィーンの俗語を覚えることが出来なかった。斯うして長くウィーンで生活すればする程、いろんなことが私の神経に引掛って、憎悪の火の手は燃え上る一方であった。この気持は、子供の頃から秘密な希望と、かくれた愛が私の心を惹きつけていたドイツの土地への、憧がれへと変って来たのである。私は今に有名な建築家となって、この憧れの祖国へ行き、祖国のためにその土地で働く悦びを想像して、独りで胸を時めかした。
或る人々には、この私の憧憬が理解されないかも知れない。しかし、母国から追われて、その神聖且つ尊い母国語のために戦わなければならない人々や、祖国と民族とのために忠実であろうとするために、迫害や圧迫に耐えて来つつある人々、また最後の時が来たなれば、懐かしの母国の腕に抱かれて永眠しようと希っている人々には、私のこの憧がれが充分理解出来るであろうと信じている。
私は、ウィーン時代のことについて、余りに長く書き過ぎたようである。
しかし何と云ってもウィーンは、私にとっては徹頭徹尾冷酷ではあったにしても、ここに於ける五ヶ年間は、又と得られない貴重な年月であった。私は何も知らない少年時代に此の都に入った。けれども、ここを去るときには最早考え深い大人になっていた。私はこの都から私の世界観や政治知識の土台を得ることが出来たのである。換言すれば、今日のナチ党の礎石は、この五ヶ年のウィーン生活によって打込まれ置き据えられたのである。若し運命が私をこの町へ導かなかったならば、そしてあの若い頃に、あれだけの修行と鍛錬とを与えてくれなかったならば、ユダヤ主義や、社会民主主義、或はマルクス主義等に対して、私の現在の態度が如何に変えられていたか、想像だに許されないことである。
ハプスブルグ王家への憎悪! ユダヤ人への徹底的な認識!
これだけの事だけでも最早私はオーストリアにとどまっている必要のない男であった。